2025年8月14日、茶道裏千家15代家元で大宗匠の 千玄室(せん げんしつ)さんが、102歳にして永眠されました。
その長きにわたる人生には、茶道のみならず「馬術」との深い関わりもありました。
同志社大学時代の馬術部在籍から、国体出場、さらには日本馬術連盟会長としての重責まで──千さんが歩んできた“馬とともにある道”には、知られざるドラマと人間味あふれるエピソードが詰まっています。
本記事では、千玄室さんと馬術の知られざる関係を調査し、千玄室さんの馬術との出会いから晩年までの軌跡とエピソードを探りました。
千玄室と馬術の知られざる関係とは?

●2025年8月14日、茶道裏千家15代家元・大宗匠である千玄室さんが102歳で永眠されました。
⦿一般には「茶道界の巨星」として知られる千さんですが、その裏側には生涯を通じた“馬術”との深い関わりがあります。
・学生時代には同志社大学馬術部で競技に打ち込み、国体出場を果たし、晩年まで日本馬術連盟会長として国内外で活躍。
★馬術は千さんにとって単なるスポーツではなく、精神性や文化交流、平和活動と密接に結びついた生涯の伴侶とも言える存在でした。
👇以下では、そんな千玄室さんと馬術の歩みを、出会いから晩年まで時系列に沿ってたどります。
馬との出会い:幼少期

●千玄室さんは、幼少期から乗馬に親しんでいたことが知られています。
・裏千家14代・碩叟宗室氏の勧めで、わずか8歳の頃から馬と関わる機会を持ち、その才能を磨きました。
⦿茶道の家元に生まれた彼の生活環境は、文化や礼儀作法に囲まれていましたが、その一方で広い屋外で馬と触れ合う時間もありました。当時、馬は単なる移動手段ではなく、人と動物の信頼関係を築く存在でもあり、千氏はそこに大きな魅力を感じていました。
⦿人間の意思と馬の動きが一体化する感覚は、後年に彼が茶道で説く「和敬清寂」の心とも通じています。
★幼少期のこの体験が、やがて大学時代の本格的な馬術競技への道を開くことになります。
同志社大学・馬術部時代:
●千玄室さんは同志社大学に進学すると、迷わず馬術部の門を叩きました。
⦿幼少期に芽生えた馬への愛情を、今度は競技という舞台で磨き上げるためです。大学の馬術部では、早朝からの厩舎作業、馬体の手入れ、騎乗練習、そして週末ごとの試合や合宿と、生活の中心が馬一色となりました。
⦿当時の千さんは、練習中でも常に馬への敬意を忘れず、力で制するのではなく信頼で馬を動かす騎乗スタイルを重視していました。これは茶道で培われる「相手を思いやる心」に通じ、周囲からも「柔らかく、それでいて芯のある乗り手」と評されていたといいます。
⦿学生時代の千さんは、関西学生馬術大会で好成績を収め、障害飛越や馬場馬術の種目で入賞を繰り返しました。特に3回生の春、関西六大学馬術対抗戦では同志社を団体準優勝に導く活躍を見せ、当時の部誌にも「冷静沈着な騎乗が光った」と記録されています。
⦿他大学との交流も盛んで、京都大学や立命館大学との合同合宿では、技術を競い合いながらも夜は焚き火を囲み、馬の癖や調教法を語り合ったといいます。合宿の朝は夜明け前から馬を引き出し、冷え込む中での調整運動──そうした日々が千さんにとってはかけがえのない青春の一部でした。
★この大学時代に培った経験と仲間との絆が、後の国体出場や日本馬術連盟での活動の礎となり、彼の“馬術人生”の黄金期を形づくる重要な時間と言えます。
国体出場とスポーツ精神:
●同志社大学での活躍を経て、千玄室さんはついに**国民体育大会(国体)**の舞台に立ちます。
・出場したのは障害飛越と馬場馬術の種目で、これは当時の学生選手にとって大きな挑戦でした。
・国体は各都道府県代表が集まる全国規模の競技会で、競技馬の輸送やコンディション調整など、普段の学生大会とは比べものにならない緊張感が漂います。
⦿千さんはそのプレッシャーをものともせず、馬と一体となった安定感のある騎乗を披露。
・特に障害飛越では、障害物を前にしても馬の耳を前に向け続けさせる巧みな手綱さばきが印象的だったと、当時の関係者は語っています。結果は入賞圏内を確保し、初出場ながらも堂々たる成績を収めました。
⦿国体での経験は、千さんにとって単なる競技以上の意味を持ちました。
・茶道の世界では「一期一会」という精神がありますが、馬術でも一走ごと、一障害ごとにその瞬間を大切にする心が求められます。
⦿大会後、千さんはインタビューで「馬術も茶道も、力ではなく心で相手と向き合うことが肝心です」と語ったといいます。
★この言葉は、後に文化人として世界に発信する彼の理念の原点といえます!
日本馬術連盟への貢献:
●千玄室さんは、選手としてのキャリアを終えた後も馬術界との関わりを絶やしませんでした。
⦿2003年、80歳という年齢で日本馬術連盟会長に就任。
・高齢での就任は異例でしたが、学生時代から国体までの豊富な競技経験と、文化人として培った国際的な視野が買われたのです。
⦿会長としての千さんは、国内の競技振興はもちろん、国際舞台での日本馬術界の地位向上にも尽力しました。
・若手選手の海外遠征支援、馬匹の輸送や飼育環境の改善、そして各国馬術連盟との交流促進など、その活動は多岐にわたります。
・特に、ヨーロッパやアジア諸国での国際会議においては、茶道家としての礼節と品格が強い印象を残し、日本代表団の信頼感を高めました。
⦿2008年北京オリンピックでは日本馬術競技選手団の団長を務め、現地での選手サポートや国際交流イベントにも参加。
・単に競技結果を追うのではなく、馬術を通じて「国際的な友好と平和」を訴える姿は、多くの競技関係者の心に刻まれました。
⦿その後も再選を重ね、2025年の改選でも12期目の会長職を続投。
・102歳にしてなお現役で活動し続ける姿は、馬術界だけでなくスポーツ界全体にとって稀有な存在でした。
★連盟関係者からは「競技経験と文化人としての教養を兼ね備えた、唯一無二のリーダー」と評され、晩年まで揺るぎない尊敬を集め続けました。
馬術を通じ晩年に至る理念と実践
●千玄室さんにとって、馬術は単なる競技や趣味ではなく、人と人をつなぐ文化的架け橋でした。
⦿戦後、特攻隊員として生き延びた経験を持つ千さんは、平和の尊さを深く胸に刻んでいました。
・その思いは茶道だけでなく、馬術というフィールドでも息づいていたのです。
⦿国際大会や連盟の会合に出席する際、千さんは競技の成果だけでなく、参加国との友好促進を重視しました。
・ヨーロッパでの馬術国際会議では、競技後の懇談会において自ら茶会を開き、各国選手や関係者に茶をふるまったこともあります。馬術と茶道──一見異なる二つの文化を融合させることで、言葉や国境を超えた交流の場を築きました。
⦿また、国内では地方大会や青少年育成事業にも積極的に参加し、馬との接し方を通じて礼節や思いやりを伝えました。千さんは「馬と向き合う心は、人と向き合う心につながる」と語り、次世代に平和と尊重の精神を託していたのです。
★晩年に至ってもその活動は衰えることなく、102歳の再選後も国内外の馬術関係者と交流を続けました。
・馬上での視界から、千さんは常に「競技は争いではなく理解のための場」という信念を見据えていたといえます!
まとめ
いかがでしたでしょうか?
本記事では、茶道裏千家15代家元・千玄室さんの知られざる「馬術」との関わりを、幼少期から晩年まで時系列でたどりました。幼児期での馬との出会い、同志社大学馬術部での青春、国体出場の経験、そして日本馬術連盟会長としての長年の貢献──そのすべてに一貫していたのは、馬を敬い、人との信頼を築く姿勢でした。競技の枠を越え、馬術を平和と文化交流の場として活かし続けた千さんの生涯は、102歳で幕を閉じてもなお、後進への道しるべであり続けます。
心より千玄室さんのご冥福をお祈りいたします。
ご覧いただき有難うございました。
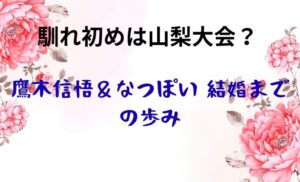
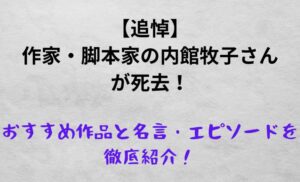
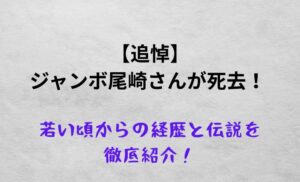
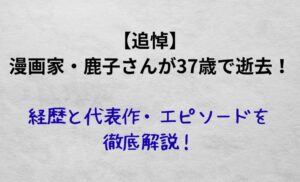
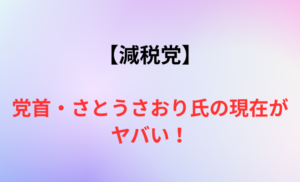
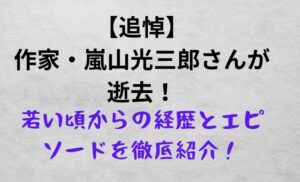
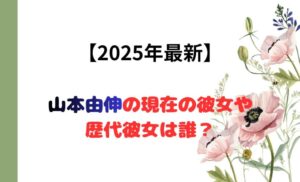
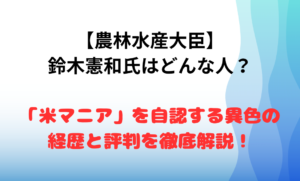
コメント