自民党所属の衆議院議員・牧島かれん氏が、最近一部メディアで「コメント投稿依頼」に関する報道を受け、いわゆる“ステルスマーケティング(ステマ)疑惑”として注目を集めています。
本記事では、報道で取り上げられたステマ疑惑の概要や争点、そして有権者と世間や専門家からの評価・評判をまとめ、今後の動向を客観的に整理しましたのでご覧ください!
目次
牧島かれん氏プロフィールとこれまでの経歴

●以下は、公開されている公式経歴や報道をもとにまとめた牧島かれん(まきしま かれん)氏のプロフィールと主な経歴です。
2025年9月時点の情報になります。
基本プロフィール
- 氏名:牧島 かれん(まきしま かれん)
- 生年月日:1976年11月1日(48歳)
- 出身地:神奈川県小田原市
- 所属政党:自由民主党(衆議院議員)
- 選挙区:神奈川17区(小田原市など)
- 主な分野:デジタル行政、IT政策、地域活性化、女性活躍推進
学歴
- 上智大学比較文化学部(現・国際教養学部)卒業
- 米国ジョージ・ワシントン大学大学院 政治学修士号(Master of Arts in Political Science)取得
主な職歴・経歴
- 大学講師:上智大学非常勤講師などを務める
- 2009年:衆議院総選挙に初挑戦(落選)
- 2012年:第46回衆議院総選挙で初当選(神奈川17区)
- 2014年・2017年・2021年:連続当選
- 2021年10月:第2次岸田内閣で
- 内閣府特命担当大臣(デジタル庁・マイナンバー・規制改革など担当)
- デジタル田園都市国家構想担当大臣
に就任。
- デジタル庁創設期:初代デジタル大臣・平井卓也氏の後任として、行政のデジタル化推進やマイナンバーカード普及に注力。
- その後:自民党デジタル社会推進本部での政策提言や地域活性化、女性活躍推進の取り組みなどを継続。
主な政策・活動分野
- 行政手続きのデジタル化、マイナンバー制度拡充
- サイバーセキュリティ強化策
- 地域創生(特に小田原・箱根エリアの観光資源活用)
- 女性の社会進出や若手議員の育成
報道で取り上げられた「ステマ疑惑」とは何か
以下は、現時点での報道をもとに整理した「牧島かれん氏をめぐるステマ疑惑」の内容・論点です。
・ステルスマーケティングとは、消費者に特定の商品やサービスについて、宣伝と気づかれないように商品を宣伝したり、商品に関するクチコミを発信する行為のこと。ステマ、と呼ばれることも多い。
情報発信に関して企業の介在があるにもかかわらず、そのことを消費者に隠したり偽ったりして行われる情報発信全般のことをいう。
引用元:Synergy
ステマ疑惑の概要
- 2025年9月、週刊文春など複数メディアが、『小泉進次郎氏の自民党総裁選出馬を支援する陣営において、ネット上で好意的なコメントを書き込ませるよう“ステマ指示”があった』という報道を行ないました。
- その報道によると、メールが陣営関係者・支持者に送られ、「ニコニコ動画(動画配信サイト)」などに好意的なコメントを投稿してほしいという指示があったとされます。
- メールには具体的な「コメント例」が複数提示されていたと報じられ、一部報道ではおよそ24パターンの例文が有ったとされています。「〇〇氏を説得できたのスゴい」「泥臭い仕事もこなして一皮むけたのね」など、賛辞・称賛を含む文言が例示されていたと伝えられています。
- さらに、例文の中には他の候補者に対して批判的な印象を与えかねない表現も含まれていたとの報道があります。
- 報道では、このメールを送った送り主が牧島かれん氏の事務所であったと報じられており、さらに牧島氏が陣営の「広報班長」的な役割を担っていたと指摘されています。
- 小泉氏陣営側は、この指示の一部は認めつつ「行き過ぎた表現が含まれていた」と釈明し、謝罪の意を表明したと伝えられています。
- 牧島氏側は、「(メールで示した)参考例を送った」「自身の確認不足で一部不適切な表現が含まれてしまった」と述べたと報じられています。
主な論点・争点
| 論点 | 内容 |
|---|---|
| ステマにあたるか否か | 指示・依頼が「宣伝・意図的な操作」であればステルスマーケティング(ステマ)とみなされ得る。一方で、政治活動・応援活動の一環として許容される範囲かどうかが争点。 |
| 表現の「行き過ぎ」/誹謗中傷の有無 | 例文の中に他候補を中傷する表現が含まれていた可能性が報じられており、そこが特に問題視されている。 |
| 責任の所在・関与の度合い | 牧島氏本人が内容をどこまで把握していたか、事務所スタッフ等が独自判断で動いたのか、指示系統がどこまで与党・選対本部とつながっていたのかが焦点となる。 |
| 政治的影響・信頼性の失墜 | 総裁選という重要な局面での「ネット操作疑惑」が党の信頼を揺るがす可能性、他陣営・有権者からの反発が広がるリスク。 |
| 法制度・ルールのギャップ | 日本の現行選挙法・ネット規制・SNS運用ルールがこうした“ネット世論誘導”に対してどこまで対応可能かという制度面の検証も求められている。 |
👇上記の主な論点・争点にもとずき「肯定派」「批判派」の視点で整理まとめてみました。
肯定派・擁護的な見方
| 視点 | 主な内容 |
|---|---|
| 政治活動の一環 | 有権者や支援者がネットで応援コメントを書くこと自体は日常的に行われており、「投稿依頼=違法」とは限らない。 |
| 違法性の不明確さ | 現行の公職選挙法は、SNS上の自主的な応援コメントやシェアを広く認めており、報道されている行為が法的にステルスマーケティングに当たるかは判然としない。 |
| “参考例”レベル | 陣営から送られた文章はあくまで参考例であり、最終的な投稿内容は各支援者に委ねられていた、という説明もある。 |
批判派の見方
| 視点 | 主な内容 |
|---|---|
| 世論操作の疑い | 金銭的な取引がなくとも、「陣営が組織的に称賛コメントを指示」すれば、事実上のステルスマーケティング(ステマ)であり、有権者をミスリードする行為だ。 |
| 他候補へのネガティブ誘導 | 報道によると他候補を下げる例文もあったとされ、選挙戦でのフェアプレーを損なう。 |
| 透明性欠如 | 政治家や陣営が関与していることを明示せず、一般市民を装った投稿が増えれば、政治コミュニケーションの信頼性が失われる。 |
「肯定派」「批判派」全体のまとめ
- 肯定派は「自主的応援」「法的根拠の不明確さ」を指摘。
- 批判派は「世論操作」「透明性欠如」「他候補へのネガティブ誘導」を問題視。

現行法は政治分野の“ステマ”を明確に規定しておらず、ネット時代の選挙活動をどうルール化するかが今後の重要課題です!
世間や有権者の声・評判の現状
●以下に、報道やSNS・ニュースコメント欄などに現れている世間や有権者の声・評判を整理!
批判的な意見
- 世論操作への不信感
- 「有権者を欺くやり方」「組織的なステルスマーケティングは民主主義を損なう」との懸念。
- 他候補を引き下げる例文があったとの報道を受け、「フェアプレーを欠く」と批判する声。
- 「有権者を欺くやり方」「組織的なステルスマーケティングは民主主義を損なう」との懸念。
- 説明不足への不満
- 「謝罪コメントだけでは足りない」「具体的な指示内容や経緯をもっと明確に」と、さらなる説明責任を求める意見。
擁護・中立的な意見
- “選挙活動の一環”とみる見方
- 「支援者が自主的に書き込むことはよくある」「違法と決まったわけではない」という冷静な受け止め。
- 「参考例を送っただけならステマと断定できない」という指摘。
- これまでの実績評価
- デジタル庁創設やサイバーセキュリティ分野での政策推進を評価する声も根強い。
- 「行政DXを進めた功績を一つの疑惑で否定すべきでない」という意見も見られる。
政治・社会的論点としての声
- ネット時代の選挙の課題
- 「法制度が追いついていない」「SNS選挙戦の透明性をどう担保するか」が議論に。
- プラットフォーム側に対しても「不自然な大量投稿を監視すべき」といった意見。
現在の状況
- ネット上では「疑惑を厳しく追及すべき」という批判がやや優勢に見える一方、牧島氏の過去の政策実績や「違法性が確定していない」ことを理由に冷静な見方も一定数存在。
- 多くの有権者は、今後の調査結果や本人のさらなる説明を注視している段階です。
まとめ:今後の影響と注目ポイント
1. 自民党内政局への影響
- 総裁選への余波
- 牧島氏が関わったとされる“コメント投稿依頼”問題は、支持基盤を持つ小泉進次郎氏陣営にも波及する可能性。
- 他候補陣営が「ネット世論操作」として批判を強めれば、党内の駆け引きに影響。
- 牧島氏が関わったとされる“コメント投稿依頼”問題は、支持基盤を持つ小泉進次郎氏陣営にも波及する可能性。
- 広報戦略の見直し
- 党全体としてもネット選挙のガイドラインや情報発信のルールを再検討する動きが出る可能性。
2. 法制度・規制強化の議論
- ネット選挙の透明性
- 公職選挙法はSNS投稿の自由度が高く、今回の件を契機に「政治活動におけるステルスマーケティング規制」を検討する声が高まると見られる。
- 公職選挙法はSNS投稿の自由度が高く、今回の件を契機に「政治活動におけるステルスマーケティング規制」を検討する声が高まると見られる。
- プラットフォーム側の対応
- X(旧Twitter)やYouTubeなど各SNSで、組織的なコメント誘導をどう規制・監視するかが議論される可能性。
3. 牧島かれん氏個人への影響
- 支持基盤への信頼回復
- 地元・神奈川17区の支持者からは説明責任を求める声が出ており、次回衆院選での票への影響は未知数。
- 党内役職や政策推進のポジションにおいて、一時的な自粛や役割変更があるか注目される。
- 地元・神奈川17区の支持者からは説明責任を求める声が出ており、次回衆院選での票への影響は未知数。
- 政策への影響
- デジタル行政やサイバーセキュリティなど、これまで牧島氏が主導してきた分野の継続性が問われる可能性。
4. 社会全体への波及
- ネット世論操作への関心増
- 有権者がSNS情報をどう見極めるか、メディアリテラシー教育や啓発が話題に。
- 有権者がSNS情報をどう見極めるか、メディアリテラシー教育や啓発が話題に。
- “ステマ”の定義再考
- 商業広告だけでなく政治分野にも適用範囲を広げるべきか、法学者・専門家の議論が進むと予想される。
まとめ
- 牧島氏個人だけでなく、自民党総裁選やネット選挙全体のあり方に波及する可能性が大きい。
- 有権者・メディアは「法制度の不備」と「政治家の説明責任」の両面を見極めながら、今後の展開を注視していく必要があります。
ご覧いただき有難うございました。
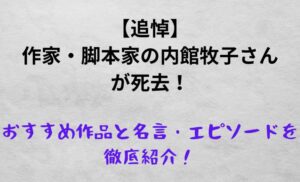
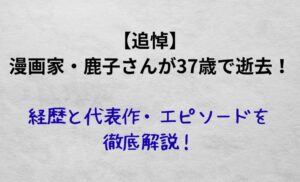
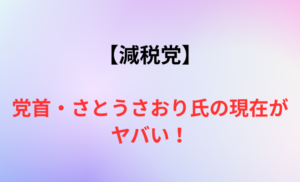
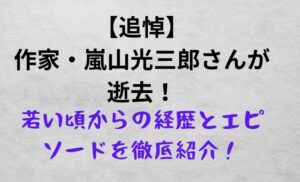
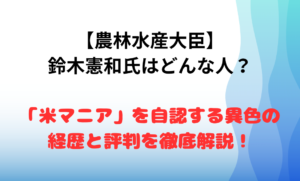
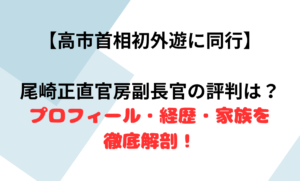
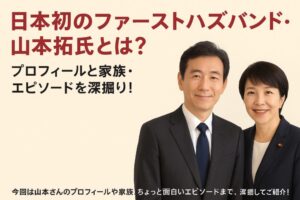
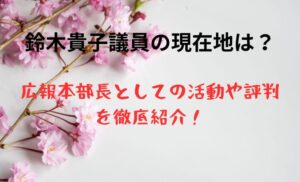
コメント