スポンサーリンク
今年のノーベル生理学・医学賞受賞のニュースは、世界中に驚きと喜びをもたらしました。
その快挙の立役者の一人である坂口志文(さかぐち・しもん)氏は、「免疫のブレーキ役」とも呼ばれる**制御性T細胞(Treg)**を発見し、自己免疫疾患やがん治療に革命をもたらしました。
偉大な科学者の功績に注目が集まる一方で、多くの人が知りたいのは**「どのような環境が、この天才を育んだのか」**ということではないでしょうか。
本記事では、坂口志文氏の**制御性T細胞(Treg)**での受賞にいたる経歴と、出身地がどこなのか、幼少期の貴重なエピソードなど、知られざる家族の絆を探りましたのでまとめて紹介します!
目次
スポンサーリンク
坂口志文氏の受賞の核心と経歴
 坂口志文氏【出典:毎日新聞】
坂口志文氏【出典:毎日新聞】
「免疫のブレーキ役」制御性T細胞(Treg)とは?
●2025年、ノーベル生理学・医学賞に輝いた坂口志文(さかぐち・しもん)氏の最大の功績は、「制御性T細胞(Treg)」の発見とその重要性の解明です。
⦿私たちの体を守る免疫システムは、外部から侵入する細菌やウイルスなどの「非自己」を攻撃する、いわば「アクセル役」の細胞で成り立っています。
しかし、この攻撃力が強すぎると、今度は自分の体(「自己」)まで攻撃してしまうという「暴走」が起こります。これが自己免疫疾患(関節リウマチ、1型糖尿病など)です。
坂口氏が発見した**制御性T細胞(Treg)は、この免疫細胞の過剰な働きを抑制する、いわば「ブレーキ役」**の細胞です。
★Tregは、免疫システムが暴走しないよう常に監視し、自己を攻撃し始めた免疫細胞を見つけ次第、その活動を抑え込むという極めて重要な役割を担っています。
スポンサーリンク
受賞の核心がもたらす医学革命
●この「免疫のブレーキ役」制御性T細胞(Treg)の発見は、医学に革命をもたらしています。
- 自己免疫疾患の治療: 制御性T細胞が十分に機能しないために起こる自己免疫疾患に対し、Tregを増やすことで病気を抑える治療法(細胞療法など)の開発につながっています。
- がん治療への応用: がん細胞は、Tregを味方につけ、免疫の攻撃(アクセル)を抑え込もうとします。Tregの働きを一時的に解除(ブレーキを緩める)することで、免疫にがんを攻撃させる、新たながん免疫療法への応用が期待されています。
★坂口氏の研究は、長らく学会で懐疑的な目で見られましたが、40年以上にわたる不屈の探求心により、免疫学の常識を覆し、現代医学に欠かせない基礎を築きました。
ノーベル賞受賞に至るまでの経歴概要
●坂口志文氏は、日本の免疫学界を牽引する第一人者であり、その経歴は、偉大な発見がいかにして成し遂げられたかを物語っています。
| 項目 | 概要 |
| 生年 | 1951年1月19日 |
| 出身地 | 滋賀県長浜市(旧びわ町) |
| 最終学歴 | 京都大学医学部医学科卒業 |
| 主な職歴 | 京都大学再生医科学研究所教授・所長などを経て、2011年より大阪大学免疫学フロンティア研究センターで研究を主導。現在は同センター特任教授、大阪大学栄誉教授、京都大学名誉教授。 |
| 受賞 | 2025年 ノーベル生理学・医学賞(「末梢性免疫寛容に関する発見」により)受賞。その他、クラフォード賞、文化勲章など多数。 |
★京都大学大学院を中退し、愛知県がんセンターなどで研究に没頭するなど、「治す医者」ではなく「解き明かす研究者」としての道を、周囲の反対や不遇な時代にもひるまず貫き通した姿勢が、この歴史的な偉業につながりました。
坂口志文氏の「研究への情熱」を育んだ場所は?
スポンサーリンク
出生地・出身地はどこ?坂口氏のルーツを辿る
●ノーベル賞学者のルーツは、日本の豊かな自然と歴史に育まれた場所にあります。
坂口志文氏の出生地・出身地は、**滋賀県長浜市(旧びわ町)**です。
⦿長浜市は、日本最大の湖である琵琶湖の東岸に位置し、自然に囲まれた地域です。坂口氏は、市立びわ南小学校、市立びわ中学校、県立長浜北高等学校を卒業するまで、この長浜の地で青春時代を過ごしました。

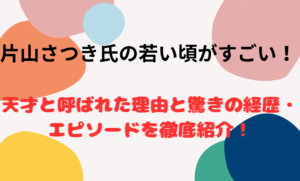
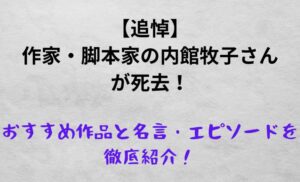
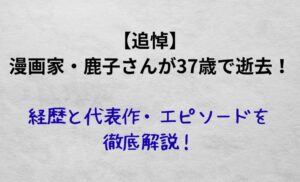
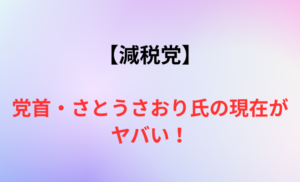
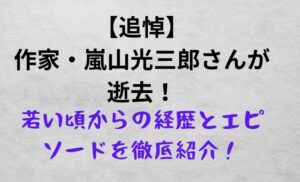
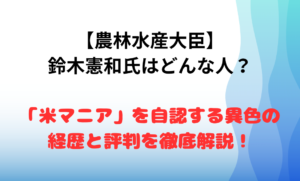
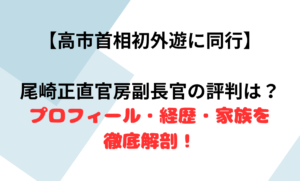
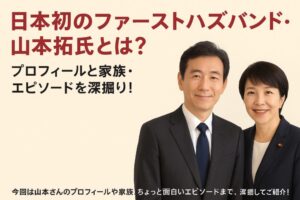
コメント