人気お笑いコンビ・チョコレートプラネットの松尾駿さんが、自身のYouTubeチャンネルで語った「SNSは素人に向いてない」発言がネット上でプチ炎上中です。
芸人らしい本音トークとも、上から目線の問題発言とも受け取れる今回の一件。
笑える話として受け流す人もいれば、本気で腹を立てる人も。
果たして“松尾流SNS論”にファンはどう反応したのでしょうか?
発言の一部が切り取られ、“松尾流SNS論”として拡散されたことで炎上状態となり、賛否両論が飛び交う事態に。
本記事では、松尾駿さんの「SNSは素人に向いてない」発言の主張内容、炎上したネット上の反応、そして今回の騒動から見えてくるSNS時代の課題を整理しまとめましたのでご覧ください!
松尾駿の「SNS発言」とは?

●松尾駿さんの「SNS発言」とは、お笑いコンビ・チョコレートプラネットのサブチャンネルで2025年9月、芸人仲間のSNS乗っ取り事件を話題にした際に語られた「芸能人やアスリート以外はSNSをやるな」「素人が何発信してんだって、ずっと思ってる」という強めの持論です。
⦿この発言は、「誹謗中傷が多すぎる」「SNSはプロ以外には向いていない」といった文脈の中で冗談まじりに語られ、SNSを含むネット上では「一般人を見下している」「上から目線」と批判や炎上が起こりました。
⦿相方の長田庄平さんが「それじゃ何も流行らない」と突っ込むなど、番組内では掛け合いがありましたが、発言部分だけが切り取られて拡散され、一部では「笑えるボケ」ではなく本気の主張だと受け止める声も上がっています。
⦿批判の一方で、「芸能人ならではの笑いのノリ」としてネタ的に楽しむファンや、「ある種正論」と感じた支持派もおり、SNS時代らしい賛否両論が生まれました。
・発言の背景には、後輩芸人への誹謗中傷・不正アクセス事件に対する怒りや、SNSのモラル低下への危機感があったとされています。
ネットがザワついた反応
●松尾駿さんの「SNS発言」に対するネットの反応は、賛否入り混じった“ザワつき”状態となりました。
批判派
- 「どんだけ高いところから見てるの?」
- 「自分たちの仕事は素人が応援してくれて成り立っているのに…」
- 「芸能人が一般人を見下している気がして不快」
★発言が“上から目線”に響いたという声や、「そもそもSNSはプロだけのものじゃない」と反発する意見が多く投稿されました。
共感派・ネタ扱い派
- 「正論じゃない?たしかにSNSは難しい」
- 「松尾ならではの笑える毒舌」「むしろコントみたい」
- 「SNSは免許制にした方が事故が減るかも」
★芸人としてのボケや笑いとして受け止めるファンもいて、「冗談っぽく言ってるだけ」「ちょっとした毒舌ジョーク」と軽く流す意見も見られました。
結果的に、SNSでは「怒」「納得」「笑い」が混在する、いつものチョコプラの“バズりエピソード”になっています。
番組内で相方の長田さんが「それじゃ何にも流行んないじゃん」とツッコミを入れる場面も、ユーザーには“芸人ノリ”として楽しむポイントになっていました。
なぜプチ炎上したのか
●松尾駿さんの「SNSは素人に向いてない」発言がプチ炎上した理由は、主に次の3点に集約されるでしょう!
発言のきっかけと文脈
⦿発言の根底には、後輩芸人・アインシュタイン稲田直樹さんのSNS乗っ取り&冤罪事件がありました。
・松尾さんは誹謗中傷や無責任な噂拡散に心底憤り、「著名人以外SNS禁止」「素人は何発信してんだ」と冗談交じりに問題提起。
「素人」という言葉選び
⦿「素人はSNSやるな」「何発信してんだ」というワードが、視聴者には“上から目線”や“一般人を見下してる”と受け止められ、強い反発を呼びました。
・芸人ならではの勢いあるトークが、動画の切り抜きで文脈を外れて拡散されたため、冗談か本音か分かりにくい状態が加速。
SNSの多様化に対するギャップ
⦿現代のSNSは一般人も情報発信・交流・ビジネス・災害時の安否確認など多目的で活用されています。
・「著名人だけのコミュニティに戻そう」「見るだけでいい時代に戻ろう」という松尾さんの極論は、時代に逆行する“暴論”と批判を浴びた理由の一つです.
★結果的に「たかが芸人が偉そうに」「一気に嫌いになった」「松尾さんには幻滅した」など失望の声が殺到。
・一方、発言の背景にはSNS炎上・誹謗中傷への悩みや現場感覚があったことも事実ですが、それが十分伝わりきらず、炎上に発展したと言えそうです!
まとめ:発言騒動から見えてくるSNS時代の課題
●今回のチョコプラ松尾駿さんの「SNSは素人に向いてない」発言騒動から見えてくるSNS時代の課題は以下の通りです。
誹謗中傷と炎上リスクの増加
⦿SNSは誰もが自由に発信できる反面、匿名性の高さから誹謗中傷や悪意あるコメントが増えています。
特に有名人だけでなく一般人もターゲットになりやすく、炎上が瞬時に拡大するリスクがあります。
これが「素人はSNSに向いていない」と感じさせる背景でもあります。
情報の正確性とフェイクニュース問題
⦿感情的に拡散されやすい偽情報やフェイクニュースもSNSの大きな課題です。
・誤解や偏見が広がることで、正しいコミュニケーションが困難になる場合があります。
発言の受け取り方の多様化による誤解
⦿特に芸人のような言葉遊びや毒舌が混じる発言は、文脈が切り取られて誤解を生みやすい。
・SNSという場での発言は受け手の解釈や拡散の仕方次第でイメージが大きく変わることを認識する必要があります。
SNSとの健全な向き合い方の模索
⦿情報発信する側も受け取る側も、リスクを理解しつつ上手にSNSを使うための教育やルール、マナーづくりが不可欠です。また、プラットフォームの適切な運営や法規制も今後の重要な課題となっています。
★今回の騒動は、SNSがもはや単なるコミュニケーションツールではなく、社会全体の課題としてどう共存すべきかの議論を促す一例でしょう。
SNS時代の言葉の重みや責任、そして利用者の多様性を改めて考える契機になりました。
ご覧いただき有難うございました。
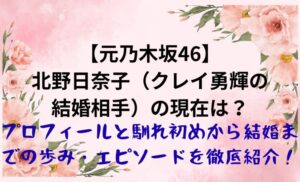
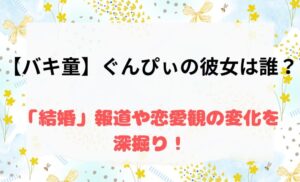
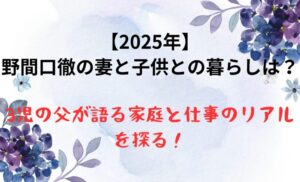
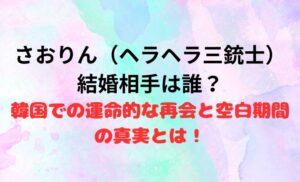
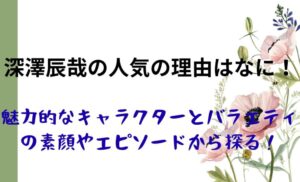
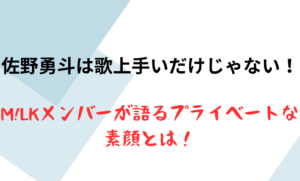

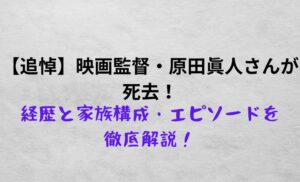
コメント